2025年11月5日(水)に一般社団法人 生成AI協会(GAIS)が主催する「第20回 GenAI 勉強会」を新宿のジョルダン社のセミナールームをお借りして開催しました。当日は、リアルとオンラインのハイブリッドで進行し、懇親会では活発な意見交換が行われました。
★GAISのメールマガジン(月3~4回発行)限定で、動画アーカイブを公開しています。メールアドレスだけで誰でも申し込み可能です。
申し込みはこちら:https://gais.jp/gais-ml
(1)AIデータセンターの進化とIOWNが拓く未来社会
講師:林 雅之 氏(NTTドコモビジネス株式会社 エバンジェリスト)

NTTドコモビジネス株式会社のエバンジェリストであり、IOWN推進室所属の林雅之氏が登壇。林氏はまず、生成AIの爆発的な進化がもたらす計算需要と電力消費の急増に言及。2040年には2020年比で十数万倍に達する可能性があるとし、AIデータセンターの立地集中や電力負荷が社会課題化している現状を示した。特に東京圏への過度な集中はリスクであり、北海道や九州など電源地近接の分散型データセンター構築の重要性を強調した。その中核概念として紹介されたのが「ワット・ビット連携(Power × Data)」だ。電力と通信を一体化し、発電所近傍にデータセンターを配置することでエネルギー需給を最適化する。これにより、地政学リスクや災害への耐性を高め、地域創生と両立した次世代デジタルインフラの実現を目指す。この構想は総務省・経産省も後押ししており、「ウェルカムゾーンマップ」などによる政策支援も進む。さらに林氏は、次世代通信基盤「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」の技術的背景を解説。電気信号を光に置き換える「オールフォトニクスネットワーク(APN)」や「光電融合デバイス」の開発により、通信遅延を200分の1、消費電力を100分の1に削減することを目指している。これにより、AI学習や推論を支えるインフラの高効率化と環境負荷低減が両立可能になるという。講演ではまた、GPU over IPの分散実証にも触れ、IOWNを活用すれば東京と北海道といった遠隔地間でも、まるで一つのGPUクラスターのようにAI処理を実行できることを紹介。これは生成AIのインフラ構築に新たな方向性を示すものだ。最後に林氏は、「IOWN 2.0」以降のロードマップとして、チップ間・ボード間通信を光化する構想を示し、エネルギー効率100倍の未来社会に向けた展望を語った。
(2)未経験から学ぶ「AI×デザイン」超入門「分かりにくい」をなくす!伝え方イノベーション術
講師:川合 卓也 氏 (「AIでゼロからデザイン」著者)

書籍『AIでゼロからデザイン』の著者であり、Shift AI社デザイン部門に所属する川合卓也氏が登壇。AIを活用して“伝わる”資料やビジュアルコンテンツを短時間で作るための実践的なノウハウが紹介された。川合氏はまず、「ビジネス資料が分かりにくい」「作成に時間がかかりすぎる」といった悩みが生産性を下げている現状を指摘。企業規模10万人で年間約90億円の損失が発生しているとのデータを示し、“伝わりやすさ”は業務効率の核心課題であると述べた。講演の中心は「AIで資料をわかりやすく変える3ステップ」だ。
① 情報の構造化:ChatGPTに「課題・解決策・導入メリット」の3カテゴリで整理させることで、文字だらけのスライドを即座に論理的に整える。
② テキストの図解化:ラグアート(RAGU-ART)などのAIデザインツールで、テキストを一目で理解できるビジュアルに変換。「100分は一見にしかず」と語り、ビジュアルは文字より600倍早く伝わるというデータを紹介した。
③ 最終調整と実務利用:生成した画像をAIデザインエージェント「ラグアート」で編集。最新機能「要素を編集」により、AI生成画像上の文字修正やレイアウト変更も容易になった。これにより、デザイナーでなくても30分で実務レベルのスライドが完成すると強調した。
さらに、Googleの生成AI「Gemini」によるスライド自動生成機能も紹介。「Googleスライド資料を作成してください」と入力するだけで、AIが即座に資料を生成。短時間で会議用プレゼンを整える例を示し、AI時代の資料作成は“思考を支援するパートナー”との協働になるとまとめた。最後に川合氏は、「AIがデザインの専門領域を民主化しつつある今、重要なのは“誰もが伝える力を持つこと”だ」と語り、参加者に向けて「AIを恐れず、まず触ってみてほしい」と呼びかけた。
(3)沖縄オープンラボ新プロジェクト「ナレッジグラフと生成AI」
講師:鈴木孝規 氏(DevRev inc. Lead of Solutions Engineer)
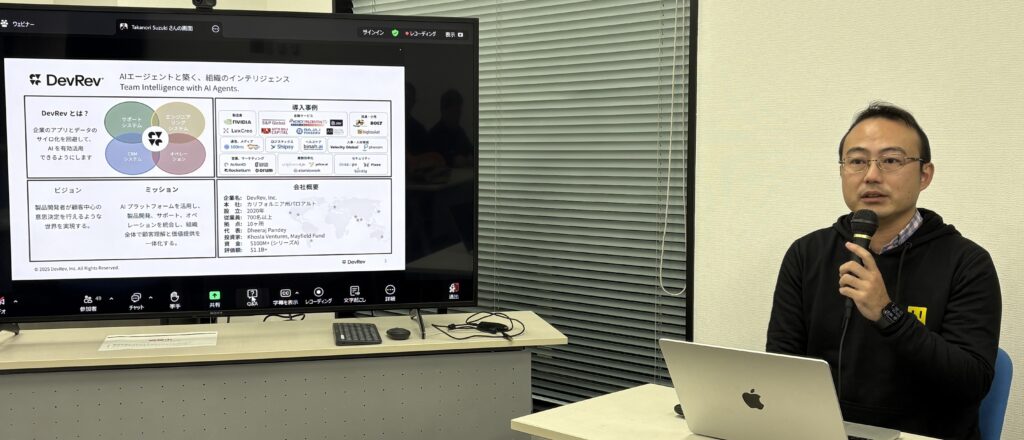
登壇したのは、OOLの山崎氏と、米DevRev社でSolutions Engineerを務める鈴木孝規氏。両者による実証的な取り組みの概要と、生成AIの実装課題を解決するための技術的アプローチが紹介された。山崎氏は、OOLとGAISが9月より相互会員となり、生成AIの社会実装を目的とした共同研究を開始した経緯を説明。今回の新プロジェクトでは、AIの正確性と再現性を担保するために「ナレッジグラフ(Knowledge Graph)」を活用する。これは情報をノードとエッジで結び、関係性を明示するグラフ構造のデータベースであり、AIが参照する知識の完全性を高める基盤技術だ。山崎氏は、「ネットワーク運用など失敗が許されない業務にLLMを適用すると、どうしても誤答が生じる。これを防ぐため、“絶対に間違えないAI先輩”をつくりたい」と語り、OOLとGAISで構築する3つの実証テーマを紹介した。
1️⃣ ネットワーク運用のナレッジ蓄積とAI検証、
2️⃣ 交通・移動データを活用した次世代乗換案内の構築、
3️⃣ 経済安全保障領域でのサプライチェーン完全性トレーサビリティ。
これらを通じ、1年ごとのフェーズ制でオープンなR&Dを推進していく方針を示した。続く鈴木氏は、米国シリコンバレー発のAIユニコーン企業DevRevの紹介から講演を開始。設立からわずか数年で評価額10億ドル規模に到達した同社は、開発者(Dev)と利用者(Rev)を結ぶ“AIエージェント基盤”を提供していると説明した。MITの最新レポートを引きつつ、「世界の企業の95%が生成AI導入に失敗している」現状を分析。失敗要因として「学習構造の欠如」「知識の分断」「評価ループの不在」などを挙げ、ナレッジグラフがそれらを補完できる仕組みであると強調した。さらに鈴木氏は、DevRevが実装するナレッジグラフを活用すれば、企業内の分散データを論理的に接続し、AIが一貫性のある説明可能な推論を実現できると解説。ラグ(RAG)やベクトル検索では困難な「否定条件」や「関係性推論」も扱えることを示し、AIの信頼性を飛躍的に高める技術であると紹介した。講演終盤では、ナレッジグラフと生成AIを組み合わせた金融機関での自動応答システム事例を披露。従来8時間かかっていた返金処理が、チャットAIによるナレッジグラフ統合で平均10分に短縮され、顧客満足度と収益性が共に向上したと報告した。最後に鈴木氏は、「AIをチームメイトとして採用する時代。人間は意思決定に集中し、AIが知識と実務を支える環境をつくる」と語り、GAISとOOLの共同プロジェクトが、日本における生成AI×ナレッジグラフ”時代の実装モデルとなることを期待して講演を締めくくった。
記事作成中★来週11/10(月) アップデート予定
